遺品整理業は「個人向けサービス」というイメージが強いですが、
実は安定した受注と売上の柱になるのが、行政や士業、不動産会社とのBtoB提携案件です。
特に最近では、
高齢者の孤独死
空き家問題
相続放棄された物件の管理
成年後見制度の活用
などを背景に、自治体や士業、不動産業界との連携の重要性が急速に高まっています。
今回は、そうしたパートナーとの「信頼関係をどう築くか」「入札や提携を勝ち取るにはどうすればいいか」について、実践的なポイントをご紹介します。
■ 連携先のニーズを理解しよう
▷ 行政(自治体・包括支援センター)の視点
孤独死やゴミ屋敷など、住民トラブルの解決を依頼できる業者を探している
市民に安心して紹介できる、信頼性の高い業者を求めている
入札制度や登録制度に基づき、対応力・社会性がある事業者を優先
▷ 士業(弁護士・司法書士・行政書士など)の視点
相続案件で出てくる遺品整理や空き家の整理を信頼できるパートナーに外注したい
顧客との信頼関係を壊さずに、安心して紹介できる業者を探している
▷ 不動産会社・管理会社の視点
空き家・事故物件の流通促進のために早期に整理・原状回復したい
遺族と直接やりとりせずに、一括対応してくれる業者を求めている
つまり、連携先にとってのベネフィットは、**「自分たちが安心して任せられる」「紹介先が満足する」**この2点に尽きます。
■ 提携に強い業者になる“5つの仕組み”
では、実際にどうすれば「紹介したい」「任せたい」と思われる業者になれるのでしょうか?
以下に、効果的な準備と工夫を5つご紹介します。
① ■ 専用パンフレットと“業者向け説明資料”を用意する
行政や士業は、利用者向けのパンフレットだけでなく、
「紹介するための資料」や「実績がわかるもの」を重視します。
過去の実績(件数・エリア・対応内容)
料金体系の例
保険加入状況(賠償責任保険など)
顧客の声・アンケート結果
有資格者の情報(遺品整理士、事件現場特殊清掃士 など)
▶ 信頼性が“書面で見える”ことが、紹介や選定の決め手になります。
② ■ 見積・報告・請求が“法人向け仕様”である
行政や士業、不動産は、書類管理が厳格です。
明細付きの見積書・請求書
業務報告書(作業内容、写真付き)
対応履歴の簡易レポート
など、法人向けのフォーマットに慣れていることが、選ばれる業者の条件です。
③ ■ 担当窓口が明確で対応が早い
紹介元が何より嫌うのは、
「問い合わせの返事が遅い」「誰が担当かわからない」などの不安です。
専任担当者がいる
電話やメールのレスポンスが早い
緊急時にも対応可能(孤独死・近隣トラブルなど)
こうした体制は、大きな信頼につながります。
④ ■ “地域活動”への参加で関係性を築く
包括支援センター主催の勉強会や、地域福祉イベント、自治会の空き家相談会などに顔を出すことで、
「話しやすい業者」「紹介しやすい人」と認知されやすくなります。
▶ 特に高齢者支援や終活関連のイベントは狙い目です。
⑤ ■ 地元士業・不動産会社と“提携メニュー”を作る
士業や不動産会社にとって、
「紹介だけして終わり」ではなく、紹介後のサービス品質が自分の評価にも直結します。
相続登記×遺品整理セット
空き家売却×整理清掃パック
成年後見×定期管理+死後事務支援
など、具体的な連携パッケージを設計し、共に提案できる関係性を築くと、提携はぐっと深まります。
■ 自治体の入札案件を狙うなら
自治体と正式に取引するためには、**入札参加資格の登録(全省庁統一資格など)**が必要な場合があります。
市区町村の「業者登録制度」に申請
指名競争入札やプロポーザルの参加情報をチェック
実績や資格があると評価点が上がる自治体もあり
▶ まずは自治体の「契約課」「住宅課」「高齢者福祉課」などに情報収集を。
■ まとめ|“紹介される側”に回る準備を
行政・士業・不動産会社との連携を強化することで、
「安定受注」「高単価案件」「信頼性アップ」が期待できます。
そして、価格ではなく“安心して紹介できるか”が選定基準となるため、
一般の顧客営業とは異なる視点が求められます。
▷ 連携強化のために今すぐできること
パンフレット・提携用資料を作る
自治体の登録制度を調べる
地域の士業・不動産会社に挨拶する
提案パッケージをつくる
報告・請求の法人対応を整える


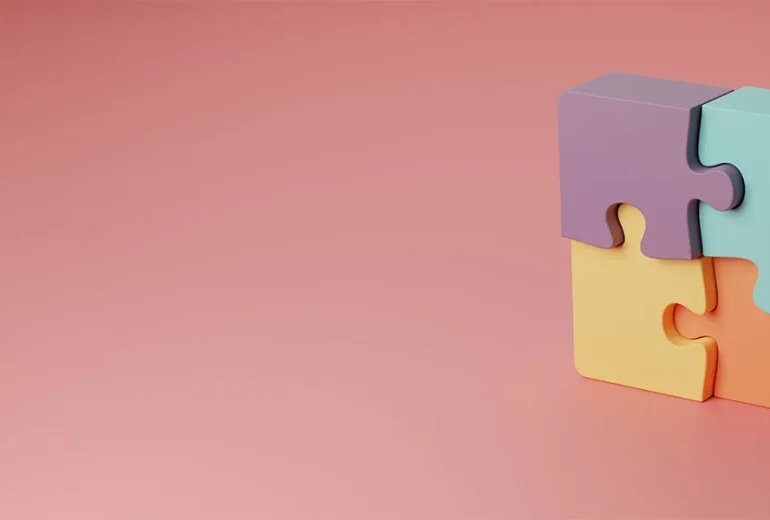













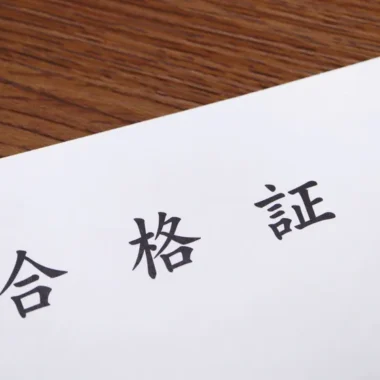










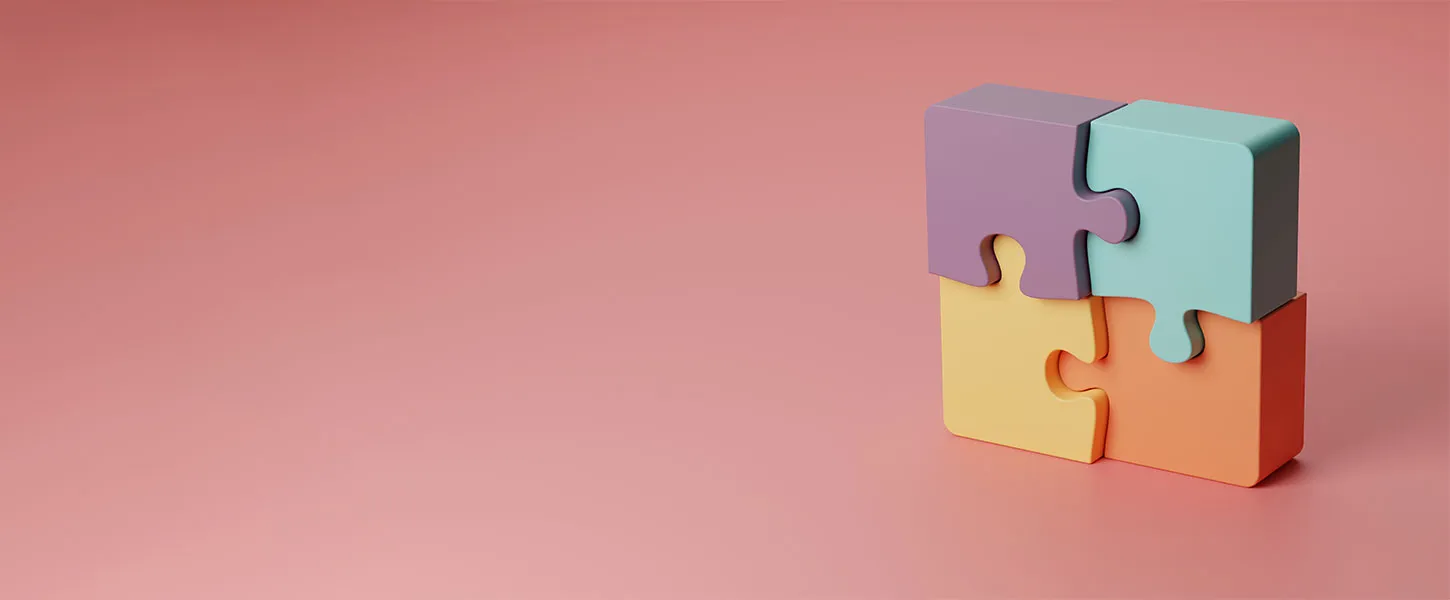
コメント