遺品整理業の現場が日々変化する中で、最近特に増えているのが「デジタル遺品の取り扱い」に関するご相談です。
スマートフォン1台に写真、連絡先、契約情報、銀行アプリまでが集約される現代。
「このスマホ、どうすればいいの?」「ネット銀行の口座があったみたいだけど、遺族も知らなかった」――
こうしたケースに現場で直面したことのある遺品整理士の方も多いのではないでしょうか?
この記事では、現場で即使える「デジタル遺品対応」の基礎知識と注意点を、全国遺品整理業協会(NRA)の視点からお伝えします。
そもそも「デジタル遺品」とは何か?
現場でよくある「デジタル遺品」は、以下のようなものです。
スマホ・パソコン本体(中に大量のデータ)
SNSアカウント(Facebook・Instagramなど)
ネット銀行や証券口座
クラウドストレージの写真や書類
電子書籍・サブスク契約
暗号資産(仮想通貨)関連のアカウントや端末
これらは、形がないものも多く、物理的に整理・処分できないため放置されがちです。
遺品整理士ができる「3つの配慮」
1. デジタル端末の扱いには細心の注意を
スマートフォンやノートパソコンは、単なる電子機器ではなく、“遺族にとっての重要な記録媒体”です。
現場で見つけた場合は、電源を入れずに「電源オフ・初期化しない」が鉄則。
勝手に触らず、「中にデータがある可能性があるためご確認ください」とお声がけすることが信頼につながります。
2. デジタル遺品の存在を遺族に伝える
遺族がスマホやPCに気づいていない場合も多く、「中に何があるか分からない」と不安に感じる方もいます。
そんな時には「最近はスマホやPCに写真や通帳アプリが入っていることも多いので、ご確認されますか?」とそっと情報提供できると、感謝されるケースが多いです。
3. 専門対応が必要な場合は連携を
暗号資産やネット証券、Google・Appleアカウントの削除など、法律や本人確認が必要な手続きは遺品整理士が介入できる範囲を超えることもあります。
その際には、全国遺品整理業協会(NRA)の紹介制度や提携士業・IT業者との連携をおすすめしてください。
現場で起きたトラブル事例と対策
事例①:スマホを処分したあとに「通帳アプリが入っていた」と遺族が発覚
→ 端末の「初期化前保管」と「確認の同意取得」を徹底。
事例②:SNSアカウントがそのままになっていて、故人の誕生日に自動通知が届いた
→ Facebook等では「追悼アカウント化」や削除申請が可能なため、遺族へ案内資料を渡すと親切です。
NRA会員向けのおすすめ対応フロー
デジタル遺品チェックリストのテンプレートや、
遺族向け案内文テンプレートを作成しておくと良いでしょう。
以下の流れを参考に作成してみましょう。
デジタル端末の有無を確認
→遺族にデジタル資産の可能性をお伝え
→不明点は「確認できるまで保管」の同意取得
→法的・技術的に難しい場合は専門家を紹介
最後に
対応力が信頼と評価につながる
「デジタル遺品」対応は、まだ業界全体でも取り組みが始まったばかり。
しかし、こうした細やかな対応が、遺族の安心・信頼を生み、他社との大きな差別化要素になります。
今後もDXが進み、こうしたニーズはますます増えていくことが予想されます。
ぜひこの機会に、デジタル遺品への理解と現場での対応力を高めてみてください。


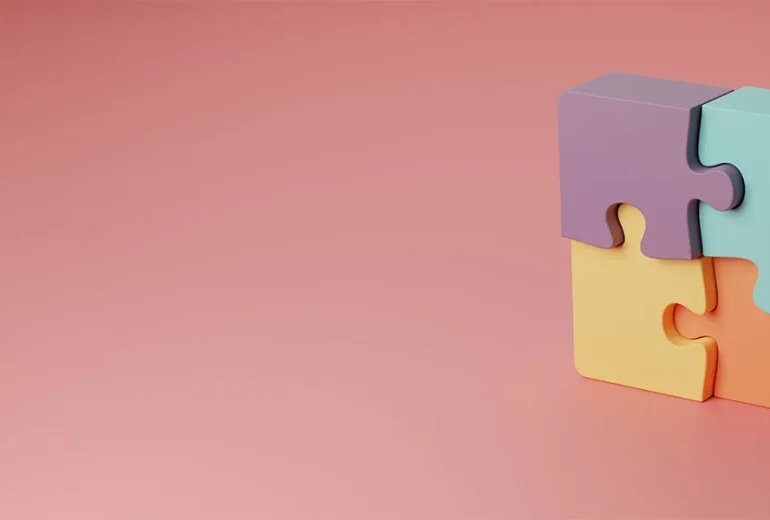













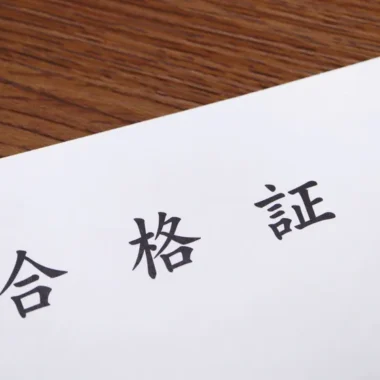








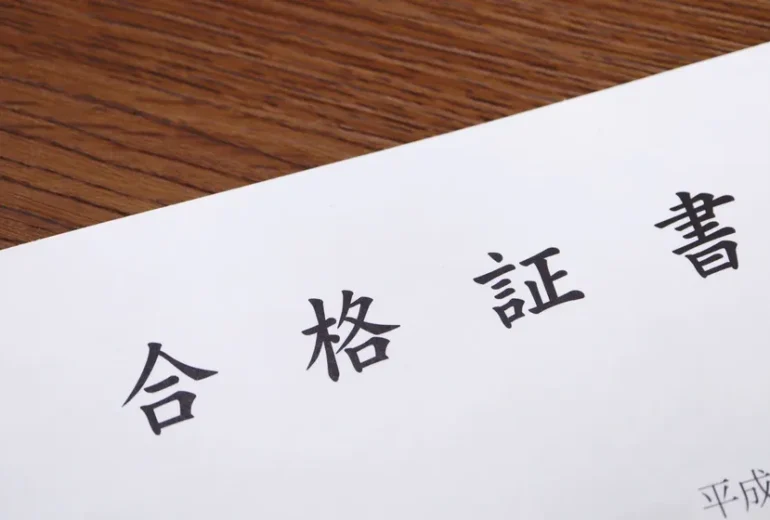

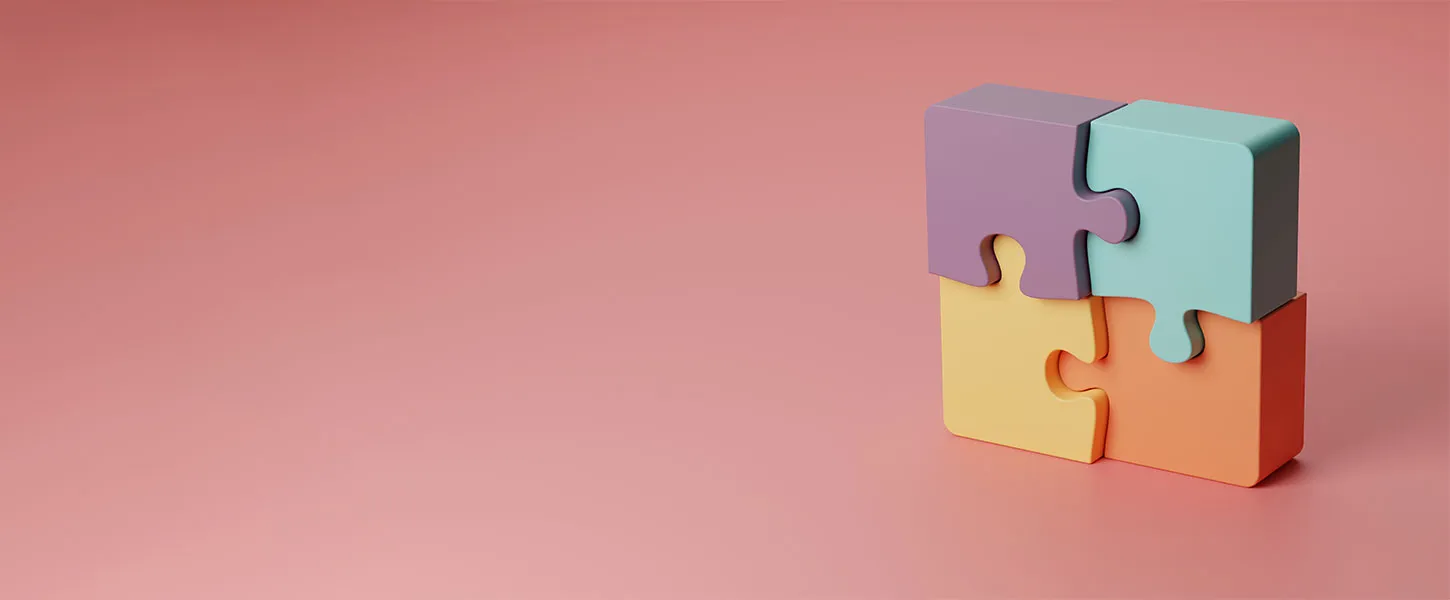
コメント