人口減少と高齢化が加速する日本において、「空き家問題」は年々深刻さを増しています。総務省の住宅・土地統計調査(2023年速報)によれば、日本全国の空き家数は約900万戸、空き家率は実に14%を超えるという異常事態です。こうした社会的課題の裏に、新たなビジネスチャンスが潜んでいることをご存知でしょうか?
空き家問題は、遺品整理業者にとって極めて相性の良い市場です。今回は、なぜ今「空き家ビジネス」が注目されているのか、そして遺品整理業者がどのようにこの市場へアプローチすべきかを、行政との連携を含めて深掘りしていきます。
空き家問題と遺品整理の相性の良さ
多くの空き家は、所有者が高齢で施設入居や死亡後に放置された物件です。相続人が管理を怠り、気づけば老朽化・ごみ屋敷化し、近隣トラブルや防災リスクの要因となっているケースが全国的に増加しています。
実際、遺品整理の依頼主から「実家が遠方で何も手がつけられない」「解体業者を呼ぶ前に片付けを済ませたい」「近所から苦情が来て行政に指導された」といった声が多く寄せられています。これは、空き家が単なる「建物」ではなく、「中身の処分」=遺品整理がセットで求められているということを意味します。
つまり、空き家の増加は遺品整理ニーズの増加に直結しており、両者は切っても切れない関係にあるのです。
市場としての「空き家」:狙うべき3つの切り口
遺品整理業者が空き家ビジネスに参入する際、以下の3つの視点でアプローチを検討すると効果的です。
1. 相続放棄・管理放棄された物件の対応
増加する「管理不全の空き家」は、相続放棄後に誰の所有にもなっていない“宙ぶらりん”の状態が問題視されています。こうした物件に対しては、自治体が介入し、行政代執行でごみの撤去や解体を行うケースもあります。
このような場面で、遺品整理業者が行政の協力事業者として入ることができれば、安定した案件受注が可能になります。
2. 不動産会社との連携による再活用
遺品整理後の空き家は「負動産」から「利活用資産」へと転換可能です。たとえば、遺品整理+簡易清掃+ホームステージングにより、売却や賃貸に向けた準備が整います。不動産会社と業務提携し、「片付けから売却までワンストップで対応可能」と打ち出せば、高齢者層や遠方の相続人から強い支持を得られます。
3. 空き家の再利用支援(地域活性化事業への参加)
近年では空き家をカフェ、シェアオフィス、子ども食堂などに活用する地域プロジェクトも活発です。こうしたプロジェクトに関わる行政やNPOと連携し、空き家の「整理→清掃→改装前の整備」まで担うことで、ビジネスの幅が広がります。
行政との連携で信頼と案件獲得を加速する
空き家ビジネスにおいて、自治体との連携は極めて重要です。多くの市区町村では「空き家対策協議会」や「空き家バンク」を設置しており、空き家所有者に対して相談窓口を設けています。
遺品整理業者がここに連携事業者として登録されれば、自治体職員からの紹介や案件相談が直接舞い込む可能性も高まります。
▽ 行政連携のポイント
地域の「空き家対策課」へ相談・営業訪問する
「遺品整理+原状回復サービス」として資料を作成する
自社の事例や保険対応実績など信頼材料を提示する
一般社団法人 全国遺品整理業協会(NRA)などの団体に加盟し、信頼性を高める
NRAとしての見解|空き家対策は地域課題解決の一歩に
全国遺品整理業協会(NRA)では、空き家問題への対応を“地域密着型事業者”の社会的使命と捉えています。私たちは、単なる片付け業者ではなく、家族の想いを引き継ぎ、地域の環境を守る存在としての遺品整理業者の在り方を重視しています。
今後、行政や不動産、解体業、福祉機関などとの連携が進むなかで、空き家対策をビジネスとして捉えるだけでなく、「地域課題の解決パートナー」として位置づけることが、遺品整理業の持続的な成長に繋がると考えています。
まとめ|“空き家”は遺品整理業の未来を開くキーワード
遺品整理業者にとって、空き家問題は今後の成長の鍵を握る市場です。ただし、単発の片付け作業だけで終わらせるのではなく、不動産活用・行政支援・地域貢献といった多角的な視点を持つことが重要です。
空き家をただの“問題”とせず、“価値ある資源”として捉え、地域とともに解決に挑むことで、あなたの遺品整理事業は次のステージへと進むことでしょう。
※全国遺品整理業協会(NRA)ではシステム提供だけでなく、教育教材にも力を入れています。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。


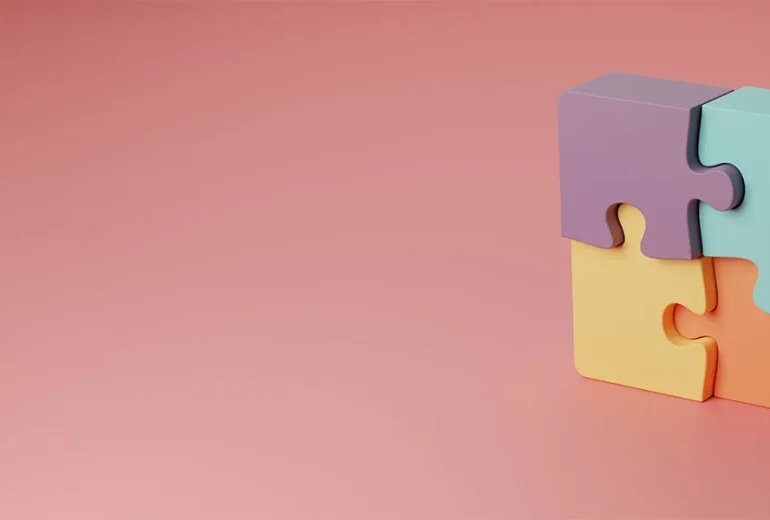




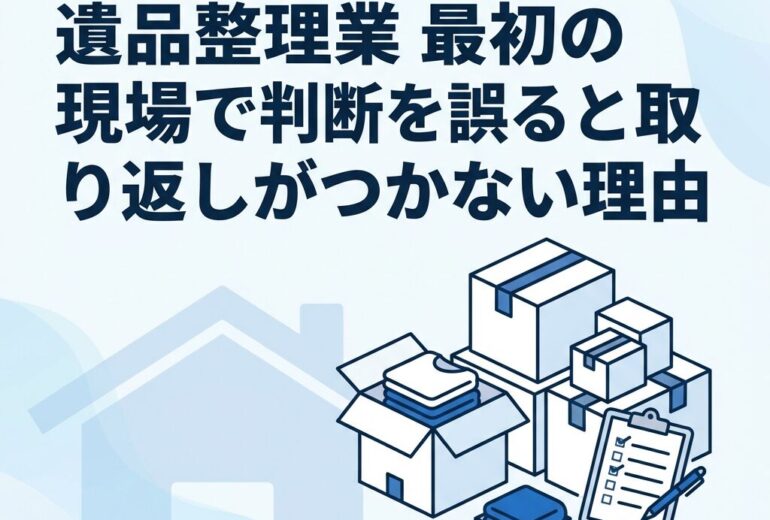








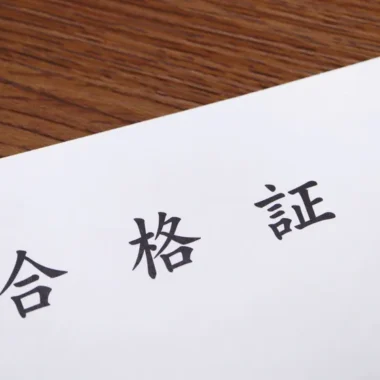


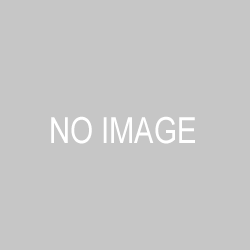




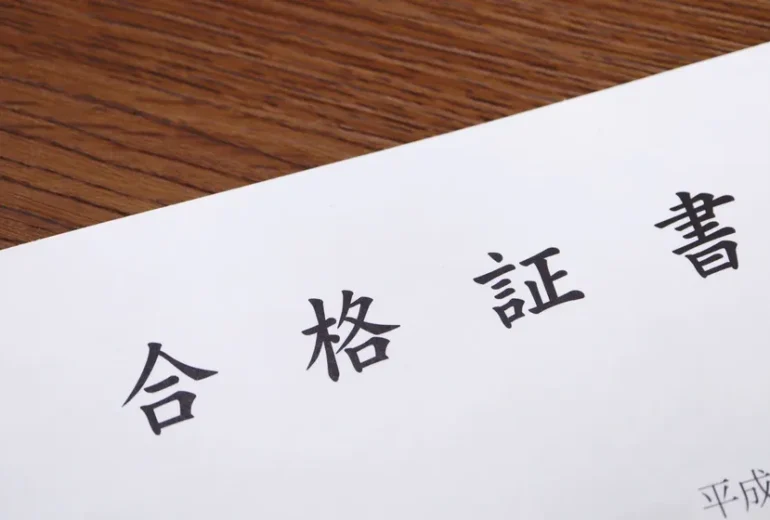



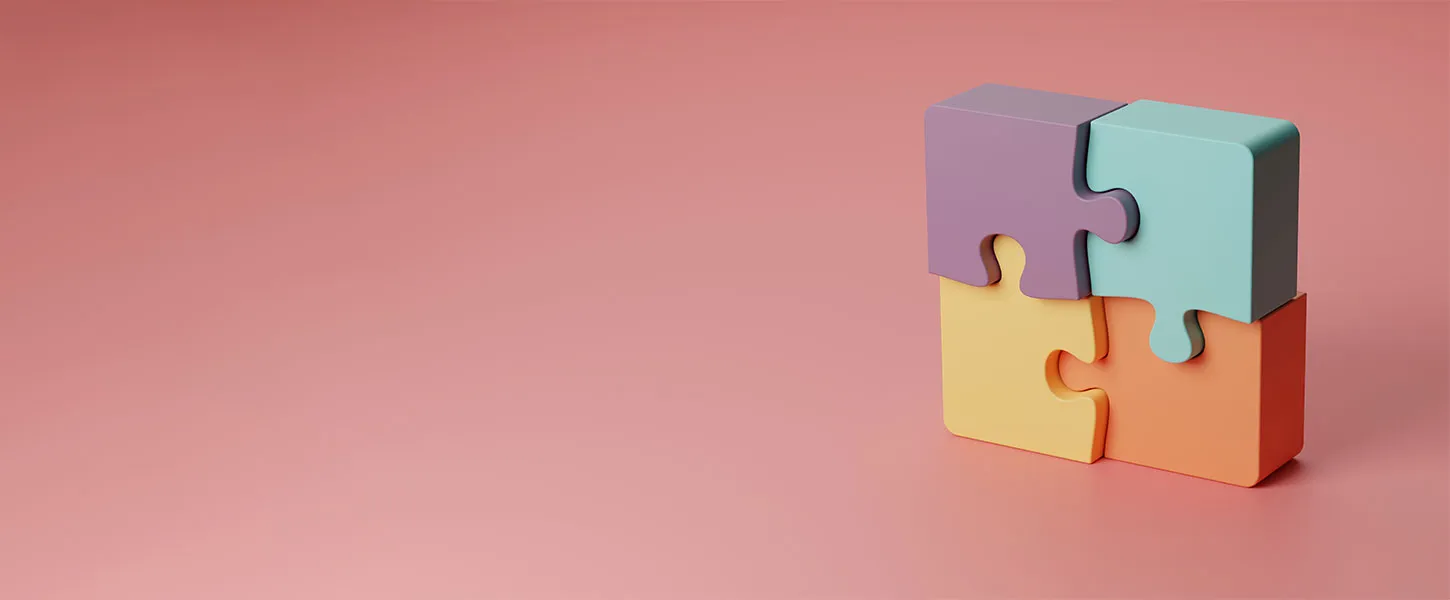
コメント